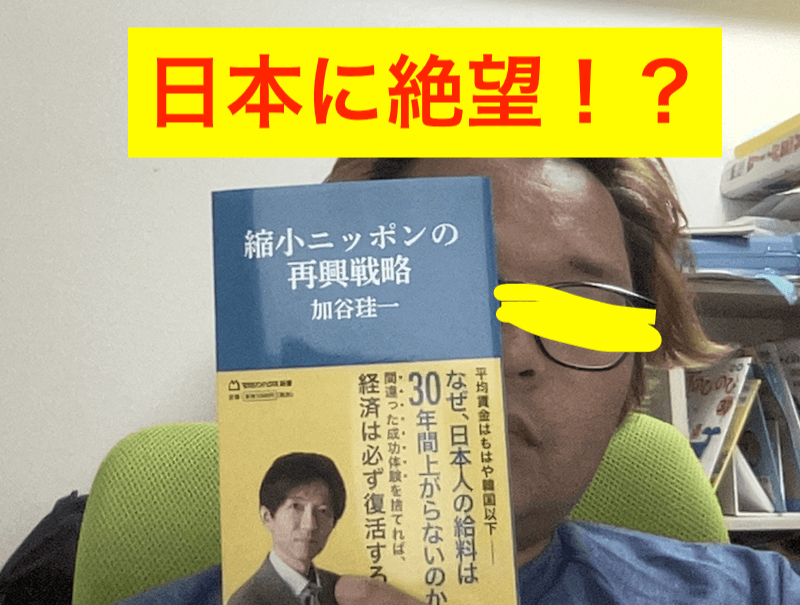
縮小ニッポンの再興戦略を読んで学んだこと
第1章 日本は経済政策では復活しない
- 経済成長は政府の経済政策によって決定されるのではない。
- 小泉改革も、民主党も、アベノミクスも経済復活できなかった。
- 学説的な経済政策は全てやったがダメだった。
- 人間は将来得られる賃金に基づいて今の消費を決める。
- 将来に対する不安心理が高いと、人はお金を使わない。
- その状態だと経済政策・金融政策が効果を発揮しない。
- 一時的にお金をばら撒いても、消費せず貯蓄に回ってしまう。
この章はいきなり勉強になりました。
日本の経済が良くないのに、アホな政治家のせいだと思っていたからです。
ですが、いくら経済政策を打っても、人がお金を使わないので景気回復につながらない。
そして、人がお金を使わないのは、将来に対する不安があるから。
というのは確かに今の自分もそうだなと納得しました。
将来が明るく、給料も上がっていくと感じていたら、
確かに生きていくのに必要なこと以上もっとお金を使いそうです。
第2章 経済成長は単なる偶然だった
この章が最も勉強になりました。
今までの自分の認識を覆してくれたからです。
章の題(「単なる偶然立った」)からして衝撃的ですよね。
- 高度成長の理由は2つの偶然が重なった
- 朝鮮特需
- ライバル不在(中国の失敗)
- 高度成長のきっかけは朝鮮戦争で得た大量のドル
- 1950〜1952年の朝鮮戦争時にアメリカから備品調達の注文が大量に舞い込んだ=朝鮮特需
- 朝鮮特需によりドルをストックできた
- そのドルが次の設備投資を可能にした
- 朝鮮特需が発生したのはまったくの偶然
- ライバルとなるべき中国が政策失敗していた
- 戦後の国共内戦
- 大躍進政策の失敗
- =アメリカの需要を満たすライバルが不在だった
日本が戦後、高度経済成長を果たしたのは、
戦争で悔しい思いをした先人たちが必死に働いたからだって思ってました。
それもなくはないと思います。
ただ、この本で書いてるように冷静に考えると、
根本的な理由は「偶然」なんだろうなと思います。
日本人は勤勉だとか、先人が頑張ったとかは、
都合の良い考え、日本を美化した考え方なんでしょうね。
日本人だけじゃなくて、中国人も他のヨーロッパ・アメリカの人も、
みんな同じ人間ですから、能力はそんなに大差ないはずです。
それなのに日本人だけ特別視するのは偏っていて、
確かに「偶然」と考えると経済成長の理由にも納得できますし、
筋も通ってる気がします。
また、有名な所得倍増計画(1960年池田勇人が提唱)についても、
政策により達成されたものではないと書かれています。
- 所得倍増計画は元々達成可能だった
- ほっておいても所得倍増する状況だった
- 後付けで「計画」と名付けて手柄を取った
なるほどです。
第3章 IT拒否社会ニッポン
タイトルからして耳が痛いです。
日本が嫌になってきます。
- 経済成長は資本×労働×イノベーションで決まる。
- イノベーションの度合いは、労働生産性が表している。
- 日本の労働生産性は戦後一貫して、主要国中最下位である。
- 現在もその差は開く一方である。
- イノベーション
- 1990年代に起きたイノベーション
- パーソナルコンピューターの登場
- ソフトウェア重視
- 2000年代に起きたイノベーション
- インターネットの普及
- スマートフォンの普及
- 1990年代に起きたイノベーション
- ハードウェア品質が低くてもソフトウェアにより解決できる
- 日本は高品質なハードウェアを高価格で作ってきた
- 中国は低品質なハードウェアをソフトウェアで解決している
- グーグル、マイクロソフト、アマゾンが例
- 日本企業のIT投資額は他国より大幅に低い。
- ERP導入の例
- 日本は無駄な業務に合わせてIT化を行う。
- 世界は効率的なITシステム(ERP)に合わせて業務を変える。
- ガラパゴス製品
- 日本でしか通用しない独自仕様
- ERP導入の例
- 高品質な製品を作っていれば売れるという考えから脱却できない。
結論、日本人は合理的な思考ができないんだな・・・と残念な気分になりました。
特にITエンジニアである私は、無駄な業務に合わせてIT化を行うというネット記事をよく目にするからです。
ガラパゴス製品も一部では日本の美徳のように言われることもあります。
確かに日本の独自文化があるっていうのは、日本人としては誇らしくなります。
一方で、世界から俯瞰した日本という視点も持っておきたいですよね。
いくら素晴らしい独自文化があっても、貧困になっていっては悲しいじゃないですか。
第4章 割愛(本で読んでね)
敗戦国だが順調に経済成長しているドイツを日本と比較しています。
日本は半製品(部品)の輸出が多い。
ドイツは付加価値の高い製品の輸出が多い。
という違いが大きいようです。
第5章 経済成長のエンジンとしての「消費」
- 輸出主導型から消費主導型の経済へ
- 輸出主導型経済の成長は、設備投資額が大きく関与する
- 輸出(外需)拡大がトリガーとなり、経済が成長していく
- 消費主導型経済の成長は、個人消費の拡大が成長エンジンとなる
- 個人消費がトリガーとなり、経済が成長していく
- 輸出主導型経済の成長は、設備投資額が大きく関与する
- どうすればトリガーとなる個人消費の拡大が起きる?
- 経済学では個人消費の拡大の方法は明らかになっていない。
- 将来が不安だと人はお金を貯め込む。
- 将来の見通しを明るくする必要がある。
- 公的年金の充実=年金制度改革
将来は大丈夫だから、今、お金をじゃんじゃん使おう!
という気持ちになったら、経済が回り始めるということですね。
第6章 日本が成長する唯一の方法
- 世界はブロック経済に向けて動いている
- 3つのブロックができていく
- 中華圏(中国を中心とし、東南アジアも含む)
- ヨーロッパ圏
- アメリカ圏
- 3つのブロックができていく
- 米国は多くの国から製品を輸入している
- 輸出元から見ると米国はお客様
- だから米国は外交交渉にも強い
縮小ニッポンの再興戦略を読んでわかること
一例として、このようなことがわかります。
- なぜ?日本が高度経済成長を達成できたかわかる。
- 経済低迷に政府が関係ないことがわかる。
- 経済成長に必要なことがわかる。
- なぜ?日本が経済成長できてないかわかる。
- 経済再生に何が必要かわかる。
この本を読んで一旦は絶望しますが、冷静に日本の置かれてる状況を理解するにはとても良い本です。
あなたも一度読んでみてください。お勧めです!
Amazonレビューも星5つで非常に高評価です。
